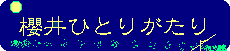「晦日走り(みそかばしり)」
大晦日だった。父と母と祖母、そして僕の四人が、居間で掘炬燵を囲んでいた。
テレビは恒例の歌合戦を映している。その画像の色が薄い。あるいは白黒のような気もする。出て来る歌手の髪型が古くさい。こんなにつまらない番組に、なぜ父たちは夢中で見入っているのだろう。無理に起きている僕は、除夜の鐘が待ち遠しくて仕方なかった。
やっと司会者が最後の歌手を紹介した。和太鼓の乱れ打ちに続き、物々しい演歌の前奏がはじまった。そこに突如、「わっ」というどよめきがかぶさった。蜜柑を剥きかけた祖母の手が止まり、父の煙管がこつんと炬燵板を叩いた。
耳を澄ました。その声は、僕の背中の方向から聴こえてきた。炬燵を立ち、通りに面した窓に歩み寄った。
ガラス戸を開けて外を窺うと、鈍く光る靄が、下組の方からこちらに迫りつつあった。それが近づくにつれて、どよめきが老若男女の声に聴き分けられるようになってきた。各々が脈格なく、短い言葉を喚いているらしい。
「テレビの音を消せ」父が、低くひそめた声で命じた。
靄は徐々に速度を落とし、まもなく我が家の門口にわだかまった。
その中に多くの人影が見えた。輪郭は個々に明瞭なのだが、目鼻立ちだけは、どう瞳を凝らしても捉えきれない。まるで古い木偶の集まりだ。いっぽう彼らの言葉は、家の中にいても聴き取れるほど、大きく、はっきりと響きはじめた。
「タカコ」「ヨシロウ」「ハルミ」、僕も知る、ここ数年のうちに死んだ人の名前だと判る。
そこに「ヨシオ!」と、いきなり大音声が轟いた。なんと父の名前だった。しかし驚きはこれだけにとどまらない。今度は「ミツヱ!」と、金切り声が祖母の名を叫んだ。その後、他の影も口々に二人の名前を呼びはじめた。
「ヨシオ・・・・・・」「ミツヱ・・・・・・」、語尾がしだいに長く交錯し、耐え難い哀切の調子を帯びてきた。居間にいる家族は誰も口をきかない。肌が凍るような怖さに耐え、僕はじっと窓際にへばり付いていた。
そんな状態で数分が経過しただろうか。ようやく背中に父の声を聴いた。
「ああしつこく呼ばわりされちゃ、かなわんのう。おばあさん、そろそろ行こか」
「ああ、そうだのん。みんなを怒らせてもいかんし。・・・・・・ほんじゃ、勝ちゃん、ワシら行くでね。お母ちゃんをよく助けてやりんよ」
二人の言葉に、僕はあわてて居間を振り返った。「おばあちゃん、どこへ行くの。お父ちゃんも待って!」
僕は、ひとり炬燵に座る母を見た。テレビは、色彩よみがえった画面に雪化粧の寺を映している。
母は言った。「ふたりとも帰ったよ」
横座には裸の蜜柑が置かれていた。皮を剥いたのは父のはずだ。そのひと房を、母はしんみりした表情でつまみあげた。煙管はどこにいったのか。
「一年目の晦日だから、『みそかばしり』が送り迎えしてくれたんだ。今にしてみりゃ良かったね。お父ちゃんもおばあちゃんも同じ年に死んだおかげで、一回余分にみんなの大晦日を過ごせた訳だ」
「どうせならあとすこし、年越しだけでも一緒にいられなかったの」
「死人は、私たちと一緒に年を越せないよ。さあ、寒いから、早く窓を閉めて」
僕はふたたび外を窺った。すでに「みそかばしり」の靄は消え、例のごとく静まりかえった通りが黄泉路のように遠く続いていた。耳を澄ませば、まだあの呼ばわりが聴こえそうな気がする。
僕は、ため息とともに窓を閉めた。ちょうどその時、除夜の鐘が鳴った。
----------------------
ところで我が故郷の人々は、亡き人の霊をこよなく慈しみ、魂魄の世に留まることをあたりまえとする思考のもと日々を暮らしている。
この間、祖母の妹にあたる鈴ばあさんを訪ね、この「みそかばしり」の話を聞いてもらった。
鈴ばあさんは、「みつゑよ、おまえも優しい孫を持ったなあ」と呟き、炭焼の煙たつ山の中腹を、さも懐かしそうな目で仰ぎ見た。あたかもそこが姉の待つ「天の奥津城」であるかのように。
了
|